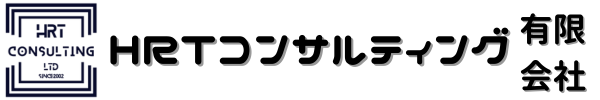ファシリテーションが機能しない現場での”あるある”

〜会議・プロジェクトでよくある停滞の正体と打開のヒント〜
「また意味のない会議で時間を取られた」
「一部の人だけが話し、ほとんどのメンバーは沈黙している」
「決まったようで何も動かない」
そんな“会議あるある”に心当たりはありませんか?
実はこれらの課題の多くは、ファシリテーション不在/機能不全によって引き起こされています。ここでは、典型的なシーンをもとに、どこに問題が潜んでいるのか、ファシリテーションで何ができるのかを読み解いていきます。
Case#1:誰も話さない、シーンとした会議
定例のプロジェクトミーティング。冒頭、「何か意見ありますか?」と問いかけるも、誰も発言せず沈黙。結局、PMが一方的に報告し、10分で終了。
◆会議の背景・問題点
会議の目的が曖昧で、発言の意味や役割が見えていない
発言しても否定されたり拾われない「話してもムダ」な空気
心理的安全性がなく、意見すること自体にリスクを感じる
◆ファシリテーションの打開ポイント
‐会議冒頭で「目的・ゴール・期待する役割」を明確に伝える
‐オープンクエスチョンで小さな発言から引き出す
(例:「最近気になっていることありますか?」)
どんな意見にもまず「受け止める・可視化する」姿勢を徹底
Case#2:話は出るのにまとまらない、時間ばかり過ぎる
活発な意見交換が行われるも、話があちこちに飛び、時間切れ。「今日は方向性が見えたので、また次回」と繰り返され、決まらないまま3回目の会議へ。
◆会議の背景・問題点
議論の焦点が定まっておらず、論点が拡散する
話の交通整理をする人がいない
「結論」や「次のアクション」まで設計されていない進行
◆ファシリテーションの打開ポイント
‐論点を「見える化」(ホワイトボード、デジタルホワイトボードなどを活用)
‐意見の分類・整理をその場で行う
会議設計段階で「結論まで持っていく論点」と「持ち帰ってよい論点」を明確に分ける
Case#3:意見が対立して場がギスギス、結局先送り
新サービスの価格戦略を議論。営業部と開発部が真っ向から意見対立。「それでは売れない」「いや、それでは赤字だ」…平行線のまま終了。
◆会議の背景・問題点
対立構造が放置され、建設的な対話にならない
感情とロジックが混在し、冷静な議論ができない
根底にある「前提の違い」が表出していない
◆ファシリテーションの打開ポイント
‐感情の整理と論点の切り分け
(例:「○○さんの懸念は何に対する不安か?」)
‐「共通の目的は何か?」を全員で確認し直す
意見の根拠・前提を棚卸しして、立場ではなく論点にフォーカス
Case#4:決まったのに誰も動かない
会議終盤、「じゃあこの方向でいきましょう」と合意。しかし数日経っても誰も動かず、タスクは放置されたまま。「あれ、誰がやるんでしたっけ?」という事態に。
◆会議の背景・問題点
決定の具体化が不十分(タスク・責任・期限が曖昧)
本人の納得感が低く、形式的に「うなずいただけ」
アクションへの意識づけが弱い
◆ファシリテーションの打開ポイント
‐会議の最後に「誰が・何を・いつまでに」を明確にする(RACIなどを活用)
‐参加者の言葉で「要するにこういうことですね」と確認し合う
次回会議に向けた進捗共有の枠組みをセットしておく
まとめ
会議や現場の「モヤモヤ」は、ファシリテーションで変えられる!
上記のような“会議あるある”は、参加者のスキル不足ではなく、場を設計・進行する力=ファシリテーションの欠如によって生まれることが少なくありません。
ファシリテーションを導入・強化することで、会議の質と効率が上がる意見が引き出され、意思決定が進む対立や停滞が建設的な議論に変わるといった変化が期待できます。