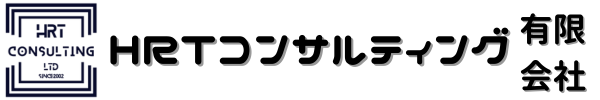ファシリテーションが機能しない現場で起きていること

よくある会議・プロジェクトの課題とその背景
ファシリテーションが正しく行われないと、会議やプロジェクトは思うように進まず、結果的に人や組織のエネルギーを浪費します。この記事では、よく見られる失敗例や課題から、「なぜうまくいかないのか?」その原因を明らかにし、ファシリテーションの必要性を改めて考えてみます。
よくある課題と背景
- #1. 発言が限られ、沈黙が多い会議
-
課題:「誰も話さない」「発言が一部の人に偏る」
背景:発言しづらい空気、目的の不明確さ、安心できる関係性の欠如
ファシリテーションの視点:場の空気づくり、目的とゴールの明確化、全員が参加できる導入の工夫が必要 - #2. 議論が脱線・ループして結論が出ない
-
課題:「話があちこち飛ぶ」「結局何も決まらなかった」
背景:論点の不明確さ、進行管理の甘さ、時間配分の設計不足ファシリテーションの視点:議論の見える化、論点整理、時間管理の徹底
- #3. 意見は出るが、対立や感情のもつれで前に進まない
-
課題:「意見がぶつかる」「空気が悪くなる」「議論が止まる」
背景:対立の放置、感情と論点の混同、立場や上下関係への過度な配慮ファシリテーションの視点:感情への配慮と論点の分離、相互理解の促進、対立を乗り越える場づくり
- #4. 決まったようで実行されない
-
課題:「なんとなく決まったけど動かない」「誰も責任を持たない」
背景:責任の所在が曖昧、腹落ちしていない合意、決定内容の具体性不足ファシリテーションの視点:合意形成プロセスの丁寧さ、アクションの明確化、合意の見える化(ドキュメント化など)
ファシリテーションが機能することで何が変わるのか?
これらの課題は、実はファシリテーターが「場の構造」「関係性」「進行」「意思決定」を適切に整えられていないことに起因しています。逆に言えば、ファシリテーションを意識することで次のような変化が生まれます。
沈黙や対立が「創造の源」へと転換される
参加者全員が納得感を持ち、動き出す状態がつくれる
決まる会議・進むプロジェクトになる
まとめ
なぜリーダーやPMはファシリテーション力を高めるべきか?
次回は、こうした課題の現場において、なぜリーダーやPMがファシリテーター的なスキルを身につける必要があるのか?その背景と効果、育成の方向性について解説します。